線路は続く13 内部補助について
内部補助とはなにか
今回は内部補助の是非について考える。
一体内部補助とは何か、という一般的説明から。
上記のような観点、すなわちある組織の中で黒字部門から赤字部門への補填が行われることを内部補助という。一方国交省は内部補助について以下のように述べている。
組織(鉄道事業者)として黒字であれば一部路線の営業係数が大きくても赤字路線の廃線を認めない、とはいいません、あくまでも赤字路線単体を考慮して、代替交通や廃線を考えるということ。
*
ここでトヨタ自動車を考える。
トヨタ自動車は日本全国はもちろん世界各国で自動車を販売している。
庶民的な車種として人気がある?「passo」の販売価格をHPから見ると、以下のようになる。
トヨタpasso価格
| グレード | 駆動 | メーカー希望小売価格*1 | 北海道地区メーカー希望小売価格*2 |
|---|---|---|---|
| X“G package”見積りシミュレーション | 2WD | 1,447,200円(消費税抜き1,340,000円) | 1,469,880円(消費税抜き1,361,000円) |
| X“G package”見積りシミュレーション | 4WD | 1,620,000円(消費税抜き1,500,000円) | 1,642,680円(消費税抜き1,521,000円) |
北海道地区を除く日本各地の価格と北海道地区の価格が掲載されている。工場から北海道への輸送費と寒冷地仕様の追加を考慮すると1台あたり約21000円1.5%コストアップになるようだ。
北海道以外での販売価格は同じになっている。
北海道地区の価格upの主なものとして北海道向けには寒冷地仕様となり冬季対策の部品設備が別途着くというコスト増によるようだ。
続いて同じくトヨタのvitzを調べた。
トヨタvitz価格
価格&グレード
燃費エンジン・
ハイブリッド
システム駆動乗車定員価格 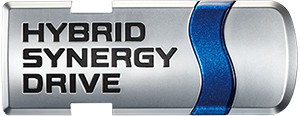 特別仕様車 HYBRID F“Safety Edition”
特別仕様車 HYBRID F“Safety Edition” 34.4km/L1.5L
34.4km/L1.5L
+モーター2WD5人乗り1,879,200円
特別仕様車 F“Safety Edition” 18.0*2〜25.0
18.0*2〜25.0
km/L1.0〜1.3L2WD/4WD5人乗り1,384,560円~
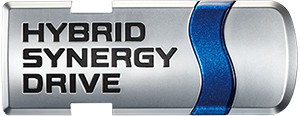 HYBRID U/HYBRID U“Sportyパッケージ”
HYBRID U/HYBRID U“Sportyパッケージ” 34.4km/L1.5L
34.4km/L1.5L
+モーター2WD5人乗り2,087,640円~
U/U“Sportyパッケージ” 18.0*2〜25.0
18.0*2〜25.0
km/L1.3L2WD/4WD5人乗り1,798,200円〜
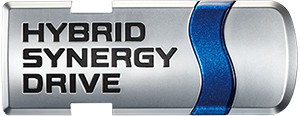 HYBRID F
HYBRID F 34.4km/L1.5L
34.4km/L1.5L
+モーター2WD5人乗り1,819,800円〜
F/F“SMART STOPパッケージ”/F“Mパッケージ” 18.0*2〜25.0
18.0*2〜25.0
km/L1.0〜1.3L2WD/4WD5人乗り1,181,520円〜
こちらは車種グレードごとに全国一本の価格だ。
*
これらの車を購入する場合当然日本各地で自動車を買い求める地域によって、製造工場からの運送費は異なるはずだが、販売価格は一定になっている。
北海道仕様車のあるpassoはその特別部品の有無で価格は異なるが、控えめに見ても北海道以外での購入価格は一定だ。
工場からの距離に比例して運送費用は逓増すると推定される、それを一定の価格で販売するということは、内部補助が行われていることになる。
調べてみたところpassoは多く、トヨタの子会社であるダイハツ池田工場製造ということになっているので、ダイハツの池田工場(立地:大阪府池田市)からの距離に比例し、京都や名古屋、東京、福岡それぞれ運送費はことなるが、その差はトヨタとして調整します、ということだろう。
つまり、大阪池田で購入すれば運送費用は例えば1000円、京都で購入すれば運送経費は同じく2000円、名古屋で購入すれば運送経費は3000円、東京で購入すれば運送経費は3500円、沖縄で購入すれば運送経費は10000円必要だがまとめて差額なしにします、すなわち大阪池田で購入する人は、沖縄の運送費用のいくらかを間接的に負担していることになる。
多かれ少なかれ、このような価格設定はどのような企業でも行われていることで、このような価格設定が出来なければ企業として成り立たないことにもなる。
これは「他の黒字線区の黒字で不採算路線の赤字を埋め合わせる」内部補助に他ならない。
より一層内部補助のわかりやすい例を。
郵便料金だ。
郵便料金の例
ハガキは1通日本全国どこへでも62円で届く。封筒は1通82円だ。
例えば東京から神奈川県にハガキを送る場合と東京から青森へハガキを送る場合で、かかるコストは異なるはずであるが、料金は同じ62円である。東京-神奈川の1通の配送コスト部分から東京-青森の配送コスト不足部分を賄っていることにより62円という料金は成り立っている。
*
JR東海の内部補助
| JR東海営業係数 | ||
| 路線名 | 平均通過人員 | 営業係数 |
| 飯田線 | 1857 | 193.3 |
| 関西線 | 13701 | 101.0 |
| 紀勢線 | 1818 | 195.0 |
| 御殿場線 | 6973 | 118.8 |
| 参宮線 | 1769 | 197.2 |
| 太多線 | 5204 | 201.5 |
| 高山線 | 3303 | 153.3 |
| 武豊線 | 8994 | 177.3 |
| 中央線 | 28648 | 90.6 |
| 東海道線 | 46366 | 86.9 |
| 身延線 | 3026 | 158.6 |
| 名松線 | 240 | 414.7 |
| 東海道新幹線 | 248560 | 60.8 |
| 注:旧国鉄で平均通過人員4000未満が特定地方交通線 | ||
(原典は週刊東洋経済「経済鉄道2018」より)
上記表で営業係数欄は、100円の鉄道収益をあげるのに経費として何円必要かを示す、飯田線は193.3円必要、名松線は414.7円かかるということだ。
これら赤字線区は実質的にJR東海の東海道線や中央線そして東海道新幹線の黒字による内部補助を受けている。
*
内部補助の弊害論
次に内部補助の弊害とされるのが、主に地方交通線の赤字穴埋めのためにまったく縁もゆかりもない都市圏の黒字から配分される、すなわち資源配分からのロスという観点である。
この点は上記にあげた会社にも考慮するとおかしなことになる。
企業とするならば、補助度合いの差はあれこのような基準を設けないことには活動できないことにもなる。トヨタの車であれカルビーのポテトチップであれ日清食品の「どん兵衛」であれ、岩波書店の広辞苑であれ郵便局のはがきであれソニーのエクスペリアであれ日本全国同じ価格だ。資源配分のロスという概念は装置産業には向かない。
また地方交通線を含め既存の路線は多くが数十年以上の歴史を持つ、かつかって鉄道省時代を含め、国鉄として一体で運営されていたという事実がある。東京から和歌山勝浦まで鉄道で行くために鉄路が引かれた。つまり東京から紀伊勝浦に行くためには東海道線と紀勢線は一体なのである。
そして産業界をみるならば上記にあげるように程度の差こそあれ、多数の企業で内部補助と同じような価格構成がとられている。
*
鉄道の運賃は以下のように国交省によるガイドラインがある。
http://www.mlit.go.jp/tetudo/sonota/10_03.html
日本の鉄道はこのままでいいのだろうか 28 -「線路は続く14 」へ進む- 紙つぶて 細く永く
日本の鉄道はこのままでいいのだろうか 21 -「線路は続く12」へ戻る 紙つぶて 細く永く
REMEMBER3.11